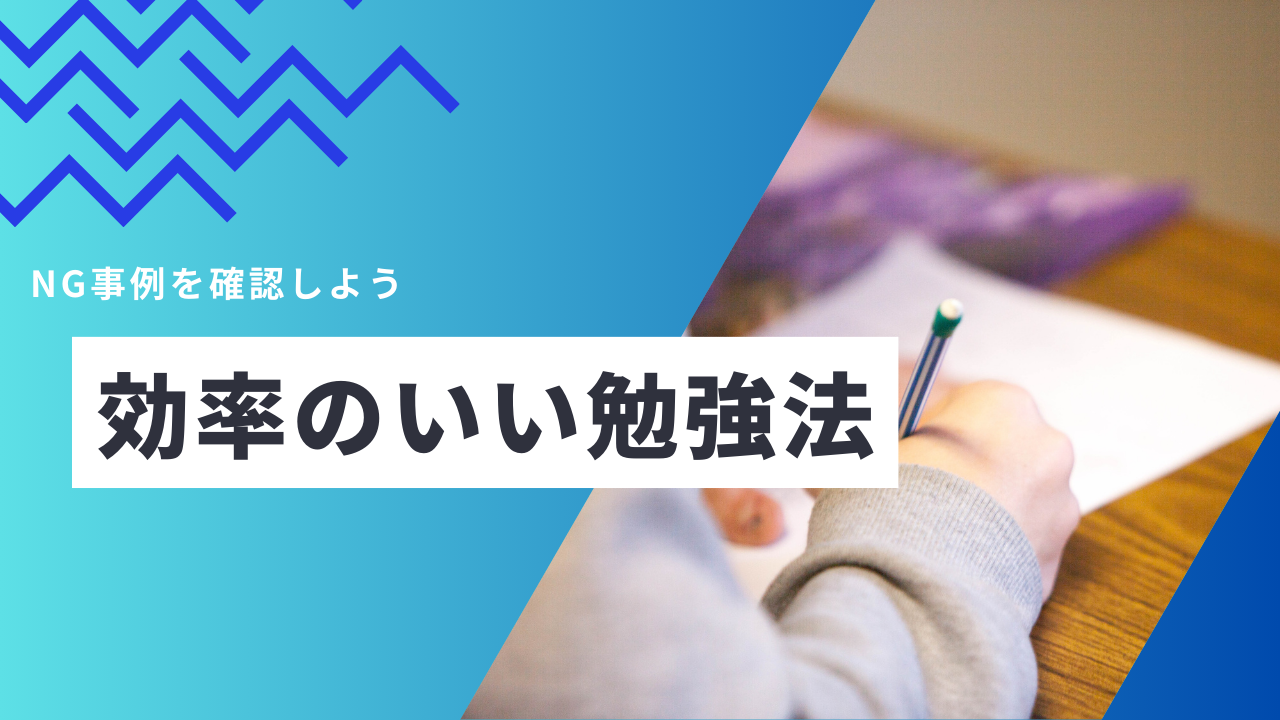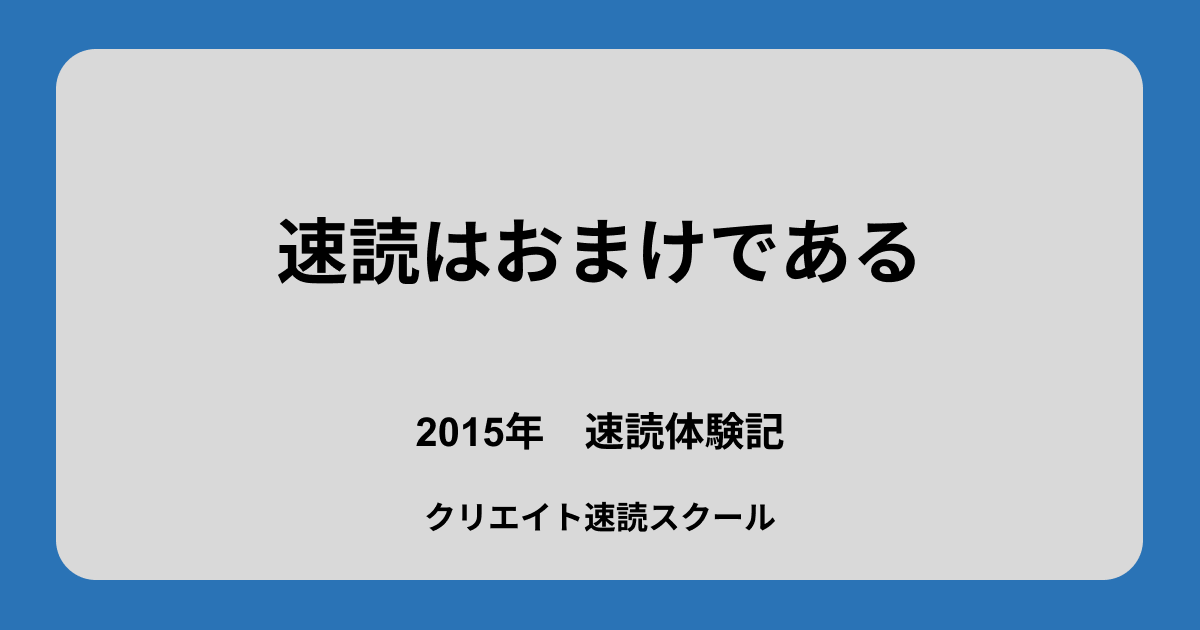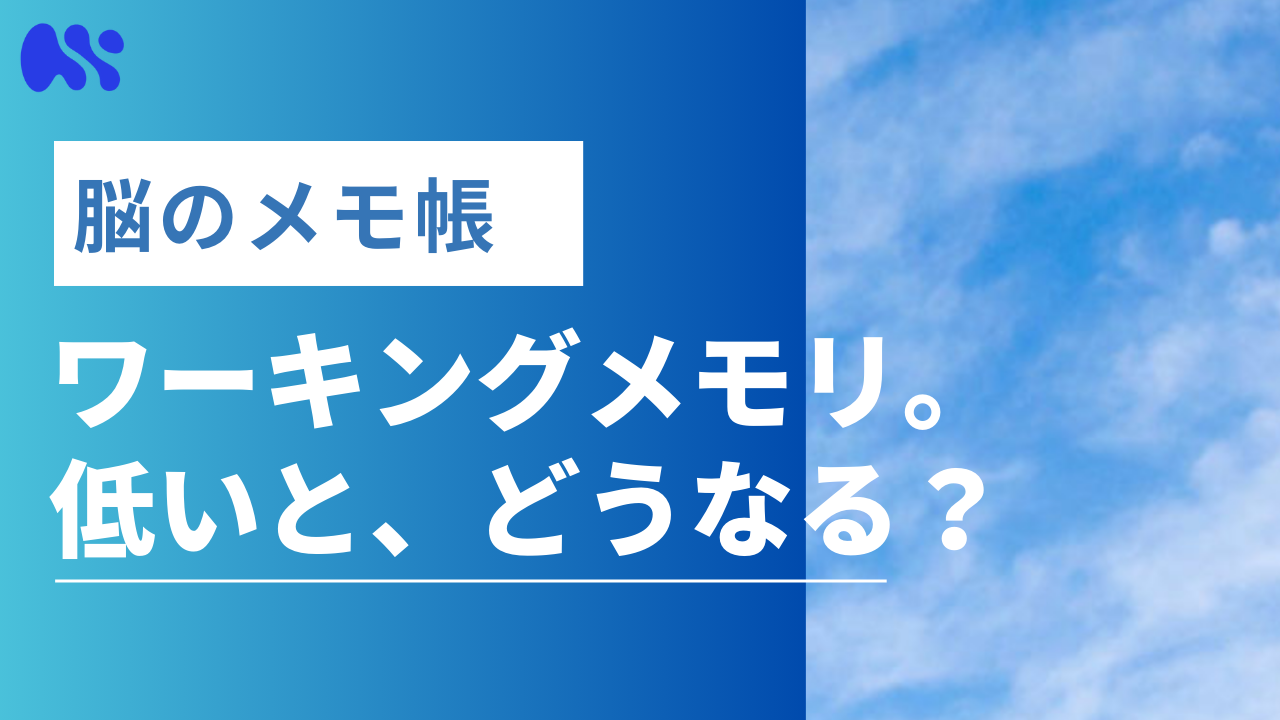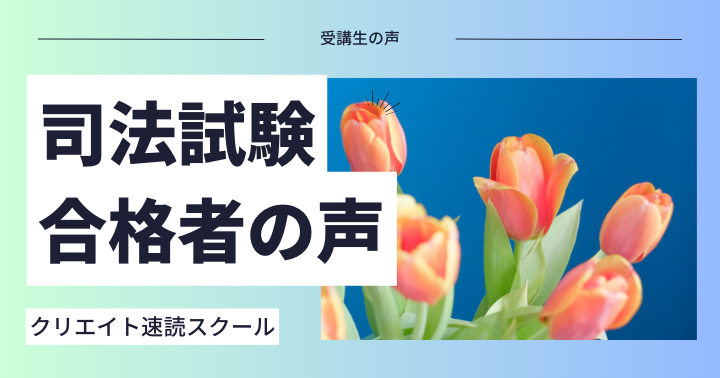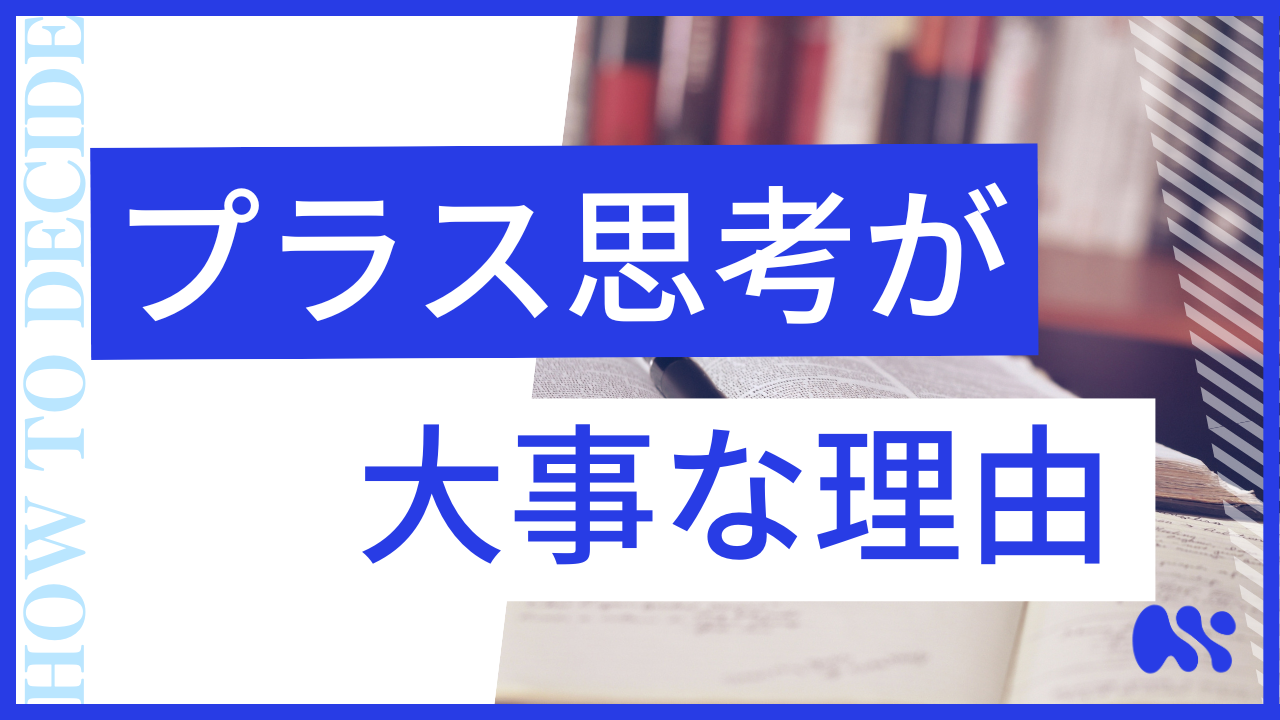
目次
この記事では、「ピグマリオン効果」「予言の自己成就」といった心理学の古典的研究をもとに、プラス思考の有用性について解説します。
ピグマリオン効果とは
「ピグマリオン」の由来
ピグマリオンという言葉は、ギリシア神話に登場する人物「ピュグマリオーン」が由来となっています。
キプロス島に住む彫刻家のピュグマリオーンは、すばらしい腕をふるって象牙の立像を彫っていたのですが、その作品の美しさは、生きた女性でさえも寄せつけないほどのものでした。作りものの女性に恋をした彼は、その像が象牙にすぎないのだと信じ込むことができず、彼女のために贈り物や臥所を用意し、大切に想う日々を過ごしていました。その様子に心をうたれた、愛と美の女神アプロディーテー(ヴィーナス)は、彼の願いを聞き入れ、美しい像に命を宿したのでした。
参考:トマス・ブルフィンチ, 大久保博(訳),1970年12月初版, 角川文庫, 『完訳ギリシア・ローマ神話(上)』, 第8章「ピュグマリオーン」
代表的な学術論文
ピグマリオン効果が初めて発表された論文の内容をご説明します。
まず、ある小学校で知能テストを実施し、その結果をもとに、成績に差が出ないように2つのクラス(A組・B組)に分けます。
次に、担任教師に対して、まったく根拠のない偽情報を知らせます。それは、「A組の生徒は、知能テストの結果、この先8カ月で急激に成績が伸びることがわかっている」というものです。
結果、8カ月後に再度実施した知能テストでは、A組の生徒にのみ、顕著な成績の向上が見られました。
このような現象が起こった理由は、次のように考えられています。
- 教師が期待によって子どもへの対応を変える
- 子どもたちが教師の期待に応じて努力をする
- 子どもたちの学力が向上する
期待を持った教師の態度や言動が、偽情報に過ぎなかったことを「事実」にしてしまったのです。
出典:Robert Rosenthal & Lenore Jacobson, September 1968, The Urban Review,『Pygmalion in the classroom』
ピグマリオン効果を説明する理論
予言の自己成就
ピグマリオン効果を説明する理論が、予言の自己成就(行動的確証)です。これは、「二者間のコミュニケーションを通して、ある種の幻想が『事実』になっていくこと」と定義されます。
予言の自己成就の実験
予言の自己成就の実験は、1970年代に社会心理学者のワードらによって行われました。
1970年代当時、アメリカでは「黒人は白人よりも劣っている。だから就職場面で採用されないのは仕方ない」という偏見が蔓延していました。
こうした社会背景をふまえ、ワードらは2つの実験を行いました。実験の内容は次のとおりです。
実験1では、研究参加者の白人に、架空の面接場面での面接官役を依頼し、その対応を観察しました。応募者は、白人と黒人です。すると、応募者が黒人であった場合のみ、白人面接官の振るまいは、ぞんざいでいい加減なものになりました。
そこで実験2は、面接官役と応募者、どちらも白人という設定で行われました。ただし、白人応募者のグループの一部に対して、実験1で黒人応募者が受けたように、ぞんざいでいい加減な振るまいをわざと行うよう、面接官役に指示を出しました。
すべての面接内容を第三者に評価させたところ、ぞんざいでいい加減な態度を取られた応募者は、そうでない場合よりも、面接の評価が低いものになりました。黒人応募者だけでなく、白人応募者の場合も、低く評価されたのです。
この実験から、「黒人は白人よりも劣っている」という「事実」は、白人面接者の振る舞いによって作りあげられたに過ぎない、と主張することができます。
出典:Carl O Word, Mark P Zanna & Joel Cooper, March 1974, Journal of Experimental Social Psychology『The nonverbal mediation of self-fulfilling prophecies in interracial interaction』
思いこみが「事実」を作り出す
このように作られた「事実」は現代にも多く存在します。「白人よりも有色人種のほうが平均賃金が低い」「男性に比べて女性の方が平均賃金が低い、議員の数が少ない」という「事実」は、思いこみによって作られたものかもしれません。
日々の何気ない思いこみや、それにもとづくコミュニケーションが、「事実」を作り出します。たとえ特定の「事実」が客観的に示されていたとしても、その背景に目を向けてみることが大切です。
身のまわりの「事実」を疑ってみよう
予言の自己成就は、上に挙げた社会問題だけでなく、身のまわりでも起こり得ます。
たとえば、「自分は勉強ができない」「〇〇は自分に向いていない」という考えは、初めは思いこみであっても、やがて事実を作り上げかねません。
逆にいえば、「自分ならできるぞ」という思いこみが、良い結果を生み出し得ることを、実験は示しています。
ここでは、マイナスの思いこみを防ぐための、簡単な処方箋を2つご紹介します。
良いところに目を向ける
1つ目は、良いところに目を向けてみることです。自分の能力に良し悪しがあるとき、悪いところばかりに目を向けていると、自分自身に対して負の期待を向けつづけることになります。良いところに注目する方が、自分自身にとっても良いフィードバックとなり、建設的です。
無意識の態度や言動を振りかえる
2つ目は、無意識の態度や言動を振りかえってみることです。気づかないうちに、自分の周囲には、思いこみを強化する言動があふれているかもしれません。
たとえば、「私は文系だから、理系科目はできない」という考えは一般的です。
しかし、「人には文系・理系の2タイプがある」という二者択一の思いこみが、自分自身を文系か理系かに決めつけ、勉強の仕方や発言に影響を与えているのかもしれません。それらの言動が、実際の成績に影響を与えている可能性は、十分にあります。
実際には、じっくり取り組めば理系科目もできるのに、できないと決めつけていては、もったいなくありませんか。
思いこみによって作られた「事実」は多く存在します。そのことを念頭に置いたうえで、無意識の言動を振りかえってみましょう。
良くなったところに目を向ける習慣づくりを
楽観的・楽天的と表現すると、どこか他人任せで頼りない印象を受ける方も多いでしょう。
しかし、自らに期待のまなざしを向け続けることは、極めて現実的な態度であり、それ自体がある種の技術といえるのではないでしょうか。
当スクールでは、毎回の授業終わりに、「良くなったところ」のメモをお願いしています。初めは気休めのように感じられる方も多いのですが、良くなったところに目を向けられることは、大きく成長する生徒さんの共通点です。
ちょっとした事柄でもかまいません。むしろ、ちょっとしたことに目を向けられることが大切です。一言だけの日記でも十分です。期待のまなざしで物事を見つめる習慣づくりに、挑戦してみてはいかがでしょうか。