- ホーム
- 体験記&インタビュー
- 体験記 '01
- 青山びすけ作品
体験記
クリエイト速読スクール体験記 '01
青山びすけ作品
三河屋のお客さま大感謝祭
青山 びすけ
会社から歩いて一分もかからないところに、三河屋という個人経営の商店がある。もともと酒屋だが、店舗の大半のスペースがお菓子や清涼飲料水、日用雑貨で占められており、「この店はコンビニである」と強く主張されれば頷けないこともない、そんな店だ。ただし、菓子パンの賞味期限三日切れが横行していること、惣菜メニューが未来永劫と確信できるほどに変化の兆しがないこと、ヨーグルトを買ってもプラスチックのスプーンではなく木ベラが付いてくること、店主が偶然とは思えない確率で釣銭の計算を間違えること、等々、多少気がかりな点が多いことも付記しておかねばならない。
木造旧家屋型コンビニ店三河屋は、よせばいいのに全国でも屈指の、自己顕示欲が強いビニール袋を用意してくれる。なんと、目にもまばゆいショッキングピンクだ。真正面には、書道の大家もびっくりの毛筆体で描かれた迫力の「河」マークがしっかりと刻印されている。こんなアピール度満点の袋を持っているところを目撃されたら三河屋の回し者だと勘違いされかねない。だから会社の人は誰でも、店から出る時はもちろん、袋を社内のゴミ箱に捨てる時ですら細心の注意を払っている。
ところがある日、同じフロアで働く杉田女史が、その迫力の三河屋袋(特大サイズ)をシャカシャカ鳴らしながら堂々と、しかもうっすらと笑みを浮かべながらわたしのデスクに向かってきた。購入したばかりとおぼしき光沢のある深緑のドレススーツに、下世話なピンクが無意味に映えている。庶民の薫りをひどく嫌う女にとってその行動は暴挙ともいえよう。何かとんでもなく辛いことがあったに違いない。触らぬ神に祟りなし、を決め込みパソコン画面から一切目を離さずにいると、デスクの上でカタッと音が鳴った。一枚の板チョコが置いてある。
「三河屋でクジ引きしたら当たったの」
えっ、クジ引き? あの、お買い得品ワゴンの中の商品すべてに定価の値札を貼っている陰険な三河屋のオヤジが、客への奉仕活動の一環ともいえるクジ引きフェスティバルを企てたっていうの?
「本当。たぶん五百円買ったら一回引けるんだと思う。四回引いたから」
えっ、四回? ってことは二千円以上の大金を三河屋なんかにつぎ込んだってこと?
「そう。インスタントコーヒーの瓶を二つ買ったの」
ちょっと待って。そもそも三河屋ごときに足を運ばざるをえなかった理由って何なの? いくら会社から一番近いとはいえ、雨も降ってないのに。
「だって仕方ないじゃない。定休日だったんだもの、いつもの珈琲豆屋。でも今日中に調達しなくちゃならないんだし。それよりね、見て見て。これも当たっちゃったの」
それは、通常より小ぶりサイズの、レトロな味わいたっぷりの座布団であった。アグネスチャンが頭につけていたような花の模様が全面に施され、色褪せかたなんかも人為的とは思えないくらい凝っている。きけば彼女が三角クジを破ると、一枚の小さな紙切れがヒラヒラと足元に舞い落ち、拾うとそれには「クッション」の文字が鉛筆で実に力強く書かれていたという。その力強さたるや、「ン」が「ソ」にしか見えなかった事実すらも凌駕してしまうほどだったというから驚きだ。しかし座布団を貰ったところで嬉しいだろうか。彼女は、叩けば確実に埃がバフッと噴出するであろう景品を大事そうに胸に抱えているのだ。やはり何か、彼女の行動指針を微妙に狂わせてしまうような辛い出来事に見まわれたに違いない。
女史は突然、口ずさんだ。ウチに最近棲みついた~、野良猫の寝床にぴったりなのよ~。
「こんなばっちい座布団、どこ探したって見つかんないでしょ?」
猫を飼っていないので座布団は要らないが、板チョコは大いに魅力だ。それにもしかしたらオヤジがどこかに頭でも打ちつけて、お客さま第一主義に改心してくれたのかもしれない。だとしたら、オヤジの慈愛に満ちた表情を拝まずにメシを食えるかってなわけで、昼食用にと、久びさに三河屋での惣菜購入を決意した。
あっ、隊長。Newオヤジを発見したでございます! とサファリ帽を被り、双眼鏡を上げ下げしながら一人芝居を演じてしまいそうな昂揚した気分は、扉をガラガラ引いて実物のオヤジを目にした瞬間すぐに萎えた。
全然、変わってねー。
フットワーク重そうなずんぐりむっくりした体型も、昼夜を問わず浮かべ続ける愛想笑いも、客の一挙一動をじっと見つめる万引き防止のオヤジビームも、一応食料品も扱ってるんだからたまには洗えよなってな感じの元紺色エプロンも、お前はさっきまで築地市場にでも行ってたのかよと突っ込みたくなる白い長靴も、全然変わってねー。
しかし一歩足を踏み入れたからには、何も買わないことはオヤジが許さない。私にもクジを試しに引いてみたい気持ちが残っている。
気を取り直し、惣菜選びに挑む。数少ないメニュー群のうち、見た目的に、腹の調子を崩す危険性の最も少なそうな鳥の唐揚げとひじきの煮付けに約二秒で決定。いざレジへ。ライスも併せてしっかりちゃっかり税込み五〇四円。さすがダテに理系は出てないよ、天才的な計算力に我ながらうっとり。奴の術中にはまってなるものかとお釣りを何度も確かめつつ、差し出された赤い塗装のダンボール箱の、カッターで刻んだらしきイビツな丸い穴に手を突っ込む。うっ。尖った切り口による皮膚へのダメージを乗り越え腕を引っこ抜くと、とうとう一枚の三角クジが我が手中に。緊張の中、開封。するとそこには濃B鉛筆で見事な「1」。おお、これが噂の力強い文字か。小指の先くらいの長さなのに左右にブレてしまったその堪え性のなさが何とも愛らしい。ドラゴンボールの悟空のカメハメ波のごとくもったいぶった後、誇らしげに「1」をオヤジの目の前にグリグリと見せつけてやった。するとオヤジが「あっ」と声にならない声を出す。何だよ今の慌てた顔、さては温泉旅行でも引いちまったかな、などと想像をたくましくしている間にオヤジはレジの下にしゃがみこみ、なにやらモソモソ探している様子。待つこと十秒。奴が満面の笑みを浮かべて立ち上がった。
「はい。これ」
手渡されたのは一対のエンジ色の細い棒。どこかで見たことがある。こいつはたしか、食事や調理のときに食べ物をはさんだりする道具だ。英語だとチョップスティックとかいったっけ。信じたくないが、和訳すると、箸。お箸だ。なぜお箸が、しかも水玉かと思っていたらコケシだか座敷わらしなんだかよくわからない不気味な顔面が散りばめられていたという結構意外性に富んだお箸が、こんなシチュエーションで登場する必要があるのだろう。一応、透明のプラスチックのケースに入っていることで新品の雰囲気が醸し出されていることだけが心の救いだ。
「よかったねー、割り箸で食べるよりずっと美味しいんだよ。知ってた?」
「はあ……」
これってもしかして一等の景品なんですか、と聞こうとしたが、ニコニコしているオヤジの目がちっとも笑っていないのでやめておいた。
ランチタイムに突入すると、早速、コトの顛末を杉田女史に話した。
「えー、うっそお。アタシも『1』だったよ、チョコ当たったとき」
「げっ」
あまりの衝撃に、思わず食事中にはふさわしくない言葉が発せられた。店主の独断と偏見で一等の景品が決まっていたのか三河屋フェスティバルは。
「やっぱりねえ。実はアタシ、今まで一度も釣銭間違われたことないんだよねえ。アンタの手前、言いにくかったけど。にしても、あのオヤジにも好みのタイプってもんがあったんだわね、きっと。オホ、オホホホ」
わたしは、どんな箸で口へ運ぼうとも結局ギトギトと油でテカって胃にもたれること必至の唐揚げと、健康食の王者みたいな超薄味の生っぽいひじきを食べ残した。そして忌々しい箸やビニール袋もろとも新聞紙にくるみ、がさつにゴミ箱へと埋めた。
女史がほれほれとチョコを差し出す。
「結構ですっ」
三河屋のオヤジなんかに好かれても嬉しくもなんともないが、明らかに差別を受けるとそれはそれでいい気はしない。それに、いつも店の売上に貢献しているのはわたしの方なのだ。
ムシャクシャした気分を静めようと早足で給湯室へ向かう。
「げっ」
流し台の上に、燦然とあやしい光を放つ物体が佇んでいる。三河屋袋だ。なんてずうずうしい。中にはオヤジのハニー・杉田女史の買い込んだインスタントコーヒーの瓶が二つ。
「ちっきしょー。今日はこれしかねーのかよ。しかもなにこの見たことねー銘柄」
だが一度おぼえた喉の渇きには逆らえない。不本意ながらも外蓋をこじ開け、中の紙蓋を引き剥がそうとした。が、なかなか取れない。こんなところにもオヤジの息がかかっているのだろうか。怒りによる指先の極度の震えと、手のひらににじむ汗とで瓶はすべり、まるでウナギのようにわたしの両手から逃げ去って行った。
「そんなに嫌いなの?」
ひっくり返った瓶に、涙ながらに訴える。
「そう、そんなに嫌いなの。もう、いいわ……ん。 あ、あれ?」
瓶の底に数字が表示されていた。賞味期限だ。
とっくの昔に切れていることはすぐにわかる。数字は1998からはじまっていた。
「杉田さん、食後のコーヒーはいかがですか?」
「あら珍しい。ありがとう」
二人ですするコーヒーは、思いのほか美味だった。
明日もクジは、引けるのだろうか。



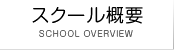




 Copyright© CREATE RAPID READING SCHOOL All Rights Reserved.
Copyright© CREATE RAPID READING SCHOOL All Rights Reserved.